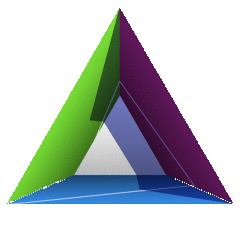騒がしい弟を持つ身として、休日にゆっくりと本を読める時間は貴重だ。
弟には弟の世界があり、わざわざ俺のいる教室に姿を見せることは殆ど無い。平日は学校の休み時間、放課後に好きな本を借りて読むことが出来る。だが休日となると友人と遊ぶ約束や勉強の予定を入れていない限りは家にいることが多くなるのは当然だろう。そして、家では弟と自分の部屋は共同であり、弟は俺のことを放っておかない。よしんば一人で遊んでいたとて、コミックに大きな声で笑ったり何やら良からぬ企みごとをしていそうだったりで、俺が無視できない。
それに加えて、俺の家の隣にはマリとサニーという姉弟が住んでいて懇意にしており、他にもオーブリー、バジルという6人組で遊ぶことが多い。自分より年下の存在が4人もいて、うち2人はとても活発とくれば、見守りが俺ともう一人いるとはいえゆっくりと出来る時間はあまりない。その立ち位置は嫌いではないが、俺だって自我ある年頃の少年だ。一人でゆっくりとする時間が欲しいと思うのは自然なことだろう。
ある日、湖にピクニックに訪れた。短な草の上にピクニットシートを敷き、バスケットから取り出されたグラス、皿、少しの食材、それと眠ってしまったケル、サニー、オーブリー、バジルが並べられている。そこらじゅうで走る、泳ぐをして楽しんで、陽気な陽射しに包まれて気持ち良さそうに眠っている。風が木々の葉を揺らす音も聞こえる穏やかで静かな時間。そのギフトに、心置きなく身を委ね、読みかけの本を開く。さて、どこまで読んだか、とページをめくれば、背中に重みと共にふわりといいかおりがする。
「ヒロくん、なに読んでるの」
「ホーキングの最新宇宙論...」
「ふぅん、難しそうだね」
「面白いよ、マリも読む?」
うん、じゃあ一緒に読もうかな。ページめくって。
マリのその声はとても近くで聞こえる。耳元で発されているので当然なのだが。マリは本を開く俺の後ろから抱きつき、肩に顔を置き、胴に手を回し、俺の手元の本を覗き込む。寝息をたてる4人がすぐそばにいる。そんなこと気にせずにマリは楽しそうに本を見る。いや、本なんて読んでなくて、俺の反応を楽しんでいるような気もする。顔に熱が集まっているのが自分でも分かる。背中に柔らかい感覚があり、本のページをめくる調子は乱されに乱されている。
「マリ、あの、本はあとで貸すから」
「うん?」
「これじゃ集中できないし」
「ふふ、ヒロくんたら分かってるくせに」
わざとだよ、と耳をくすぐるような声がする。そうだ、マリは宇宙の本になんて興味ない。昔からそうだ。でも、分かっていたところでどうすれば良いというのだ。天気のよい日に今日はピクニックをしようとみんなを誘ったのも、みんなが元気に走り回るような遊びに誘導したのも、走り終わったあと皆が満腹感を覚えるような軽食を用意していたのも、マリの計算で、俺だけが眠らないのも、マリの計算だとしたら?それに逆らう道理もない。そうして俺は彼女の計算のままに彼女のことを今日も好きになっていいのだろうか?振り返って見る彼女の表情からは、それは分からない。
.
ヒロマリ(omori)
小悪魔7題
2.思わせぶりはきみの特技だ (計算された優しさも)