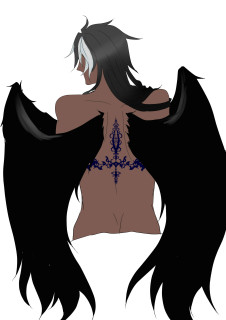2013-8-11 10:03
負け犬ヴェンデッタ
ぜーんぶ投げ出して。
そうやって逃げ出せれば、良かった?
知るか、馬鹿。
問われた言葉に、脳内で答える。
無表情に、無言で私は早く終わらないかな、なんてまるで他人事のように眺めていた。
痛みは既に麻痺してて、身体の何処を見ても笑えるくらいに怪我だらけ。
現在進行形で怪我は増えて行ってる。
薄暗い此処は多分地下牢かなんかで、目の前のイケメン眼鏡は多分、いつか読んだ漫画の登場人物で、この世界は箱庭の中で。
そんなところに、突然現れた見慣れ無い格好の私は不審者以外の何物でも無くて。
当然捕まるし、当然聞かれてる意味なんてわかりゃし無い。
字は読めないし、聞き取れる単語もごく僅か。
敵だと認識されるまでに、半日も要らなかった。
敵もくそも、私は壁を破壊できる程デカくはなれ無いんだけど。まあ、伝える術がない。理解させる根気も既に失われた。
あ、最後の爪が無くなった。
「声もあげないなんてすっごいね〜」
ケラケラと笑うも、目が笑っちゃいない。
でも、好奇心は一杯ってなんてマッドな奴。まあ、そういうキャラだったか。
不意に二つ分の視線を感じて、目の前の存在から目を逸らす。
瞬間、鳩尾を蹴り上げられた。
げぶ、もう胃液もでやしない。どうにも拷問中に気を散じることを目の前の存在は許し難いらしい。
ゲホゴホと噎せながら視線を戻せば、ああ、ほら機嫌も戻った。
「もー、ちゃんと反応返してくれないとねー?」
反応も糞も無いんだけどね。
回復する事も無きゃ、巨人化もできゃしないって結論はもう随分と前に出たろうにな。
視線は気配を伴って、私の牢の前で止まる。
「…ハンジ、何故まだ彼女に対しての拷問を続けている?」
何を言っているのか、わかりゃし無い。
けど、何と無く咎める様な視線が目の前の存在を窘めた事は分かった。
目の前の存在は肩を竦めて、一言何かを言い返す。
「んー、わかってる癖に〜」
会話は聞き取ろうとももはや思ってない。
そんな中で、背が低い男が私の目の前に立った時だった。
ズン、と言う重々しい音。
もはやそれは轟音に近かったけれど。
天井が崩れ、壁が倒れ、目の前にいたはずの三人は腰に付けた装置で安全圏へと退避していた。
目の前にはでかい口、でかい目。
で、私の腕には鎖、足には錘。
どうやら、処刑法はこの世界では有り触れた、私にとってはとんでも無くあり得無いものになったようだ。
さて、目の前の巨人は荒い息を吐き掛けてくる。私以外には興味がないようで。
ずーっと見ていた。
観察していた。
何の感情も乗せ無いまま。無色透明の視線は、巨人を捉えている。
「動かないねー」
間の抜けた声。
言葉はわから無い。声は判別できる。
拷問をしていた彼女だろう。
ともあれ、此処で死ぬのか、こんなところで。何もせず、何も出来ず、何も成せず、何物にもなれ無いまま。
約束を破り、生きる事を放棄して。
ああ、足掻けば良かったのか。それとも、このまま恐怖と共に訪れる死を享受するか。
「…そんなん、もう、どうだっていいや」
それじゃあ、一つ、賭けに出ようか。
魂を、賭けよう。
ふふ、好きだった漫画の台詞を一つ落として、さあさ、皆様準備はいいか。
ああああああっ
間延びした雄叫びと共に遂に巨人は私に向かって口を開けて迫ってくる。
ばづんっ
凄まじい音がした。
断ち切られる音にしては何処か固そうな音が、した。
何をやったのか、上から見ていた三人は理解して驚愕した。
まるで巨人を受け入れるかのように鎖で繋がれた左右の腕を広げて、巨人へと差し出す。
巨人が狙いを付け、その口を閉ざそうとした刹那、彼女はふわりと後ろへ倒れこむようにその歯列を避けた。
鎖は慣性に従って巨人の口へ。
食い千切られた鎖。
やれやれ、と私は再び私へと狙いを付けた巨人を見る。
知性も、理性も、本能も、何処か足りてい無い気がする。
哀れと言えば哀れだけれど。
「死んでやるわけにもいかないから…」
そこ迄言って、私は駆け出す。
ボロボロの身体で走る。
ぐちゃぐちゃの地下牢を駆け抜けて行く。
無論、巨人も壁を薙ぎ払いながら追いかけてくる。
やがて、目当ての場所へ辿り着いた。
視界の端には安全圏で悠々と私を見つめる三対の瞳。
助ける気なんてありゃしねぇんだろう。
それで、いい。それが、いい。
「さあ、おいで…もう一勝負しようじゃあ無いか…」
静かに、告げて、私は巨人をじっと見つめる。
ああ、素直な子だ。
ガラガラと瓦礫を作りながら私へ一直線にやってくる。
ああ、愚かな子だ。
その直線は、お前にとっては命取りなのだから。
ガラガラ、ガラリ。
音が途切れ、異様な振動が始まる。
「それでもね、死んでやる事は出来ないんだ…だから…」
振動が大きく強くなる。
当たり前だ私を追って散々この巨人はこの城を支えて居た要の石壁を悉く、尽く、破壊したのだから。
ぐらりと傾き始める。
巨人のいる、彼方と此方。
何が違うかなんて、見ればわかるだろ。
此処は、此処だけは崩れない。
此処は、この城で唯一独立して作られて居たから。
だから、此方と彼方は分かたれる。
「だからっ…」
ずり、ずり、めき、めしっ
巨人が奈落へと落ち始める。
地下牢の格子窓の向こう側は、皮肉にも獄中死した者の為の墓場。
落ち始めた巨人は必死に私へと腕を伸ばす。崩落が始まった彼方側。
潰されれば、動けなくなるだろう。
ああ、哀れな子だ。
瞳に映った私は、なんて、邪悪だろう。
「堕ちて行け、苦しみながら。この地下牢を怨嗟を引き摺って。堕ちて行け…」
ああ、なんて綺麗な子だろう。
最後迄、最後の最後迄、私しか見なかった。
彼女が、私の隣の牢にいた少女に似ているだなんて、ああ、知っていた。
語る。語って逝く。
目が語る。
「…分かった」
轟音、砂埃。
散った赤に混じる無色。
三人は信じられなかった。
無気力な、無色透明な、罪人が、巨人を駆逐する。だなんて。
ハンジが声をあげようとして、失敗した。
崩れ落ちた城跡へ躊躇いも無く私が飛び降りたから。
そして、その先には死に損なった巨人。
手枷、足枷を引き摺りながら、私は駆ける。
ガラリ、ガラリ
巨人はまだ、生きているのに、私が走って行くから、エルヴィンが叫んだ。
ああ、本当は、名前位なら聞き取れてた。
だから、私は行かなきゃあ、ならない。
下半身は完全に押し潰されて、腰からずるりと千切れている。
ドロドロの赤が辺りを焼く中で、私は走る。
ああ、やっぱり強い子だ。
「おおいえ、お、え、あ、い…」
ああ、この世界で出会ったたった一人の友人よ。
「私は死んでやる訳には、いかない。だから、………」
彼女にだけ聞こえるように、そっと告げてやれば、彼女はやっと目を閉じて、力を抜いたから。
「寄越せ…」
振り返りもせずに突き出した手に握らされる重み。
歩み寄り、抵抗の無い巨人の項を、削ぎ落とした。
「聞き、届けたり…」
ぽつり、零して、私は渡された替刃をその辺に突き立てて、座り込む。
熱風が吹き荒び、哀れな巨人は崩れ去った。文字通り、跡形も、無く。
握りの部分、柄の部分が無いままあらん限りの力で刃を振るった両手は無残に抉れて、血が滴る。
その熱さと苦痛が、私の正気と意識を繋ぎ止めていた。
「見事なものだな…」
背後で三人のうち、恐らく一番背の高い男、エルヴィンが何かを呟いた。
聞き取れない言葉に、理解の及ばない価値観と、世界観。
努力を怠った、言われればそうかもしれない。
分からない、足掻いた。
けれど、伝わらず、誤解され、憂き目に合って諦めた。
諦めなければ、また違う結果だったのでは無いだろうか。
ああ、くそ。知らねぇよ。
無い物ねだりしてるだけだ。
どう足掻いても言葉が通じなければどうしようもなかった。
名前だけでも聞き取れるようになるのだってかなり掛かったのだ。
「あちゃー、実は即戦力だったりしたのかなー…」
拷問していた女、ハンジが何かを言った。
分かりゃ、しない。
飽く迄、音としての認識でしかない。
ぐい、腕を引かれて無理矢理に立たされた。
何処もかしこもボロボロなのだから、あまり乱暴にしないで欲しいものだ。
痛みは既に麻痺して熱源として感覚が誤認して居るけれど、うっかり肩でも外れればはめるのだって痛いのだ。
再び無色透明に戻っているだろう死んだ目で、腕を掴む小柄な男性を見る。
確か彼はハンジに、リヴァイと何時だったか呼ばれていた気がする。
「…何故、巨人の弱点を知っていた」
その問いに、明らかに空気が凍り、エルヴィンとハンジの双眸に疑惑の光が浮かんだ。
けれど、何を言われているのか私にはわかっていない。
答える術を持たない私に、彼は、彼等はなんて高度なものを求めるのか。
雰囲気で質問されているのは感じ取れる。だが、それだけだ。
内容は知る由もない。理解出来るものでも無い。
「答えろ…」
だから、どうやって、だ。
知ったこっちゃない。分からないんだ。
なんて言ってるんだ。アンタは、アンタ達は何を聞きたいんだ。
「だったら名前位は教えろ…」
無色透明に諦めを滲ませて、私の知る言語で答えてやった。
「何て言ってるのか、わからない。理解出来ない。答えられない」
今度は相手がポカンとしている。
ああ、やっぱりダメか。
何度も試した言葉を飲み込んで、再び黙った。
「やはり、か…彼女には我々の言葉が通じていないその逆も然り、だろう。我々は彼女の言葉を理解出来ていない…」
エルヴィンが苦い顔で何かを言った。
やっぱり分からないから、私は面倒になって、掴まれた腕を振り払って歩き出した。
巨人が居たあたり。
もしかしたら、なんて淡い希望があった訳じゃあ無い。
単に、形見の一つでもあれば、墓を作ろうと思っただけだ。
奇しくも此処は罪人の墓場だから。
そんな希望を打ち砕くには充分なほど、辺りは真っ黒こげで。
ああ、やっぱり彼女は永遠に失われたのだろう。
ああ、暑い、熱い。
そう言えば裸足だった。
「何処へ行くつもりだ…」
わから、ない。
わから、ないよ。
逃げたい、逃げたい。
帰り、たい。
再び腕を掴まれた時、ようやっと私に感情らしい感情が戻ってきた。
今迄の溜まりに溜まった全てを吐き出す様に、唯一の友人の死を悼む様に。そして、命を奪った罪悪感と恐怖に、喚く様に泣いた。
叫んで喚いて、狂乱したように、泣き叫んだ。
子供の様に。迷子になった子供の、様に。泣くしか出来なかった。
怖い、辛い、苦しい、痛い、寂しい。
全部、全部。誰にも言えず、理解されず。
独りで、抱えて。
命を、賭けた。
わんわんと泣き続ける私に、三人は何も言えないまま黙りこくる。
やがて私は泣きつかれて、泣いたまま意識を失った、のだろう。
記憶が途切れているから。
屠り合う、盟友。
(赦さないで。だから、私は生きていく)
+